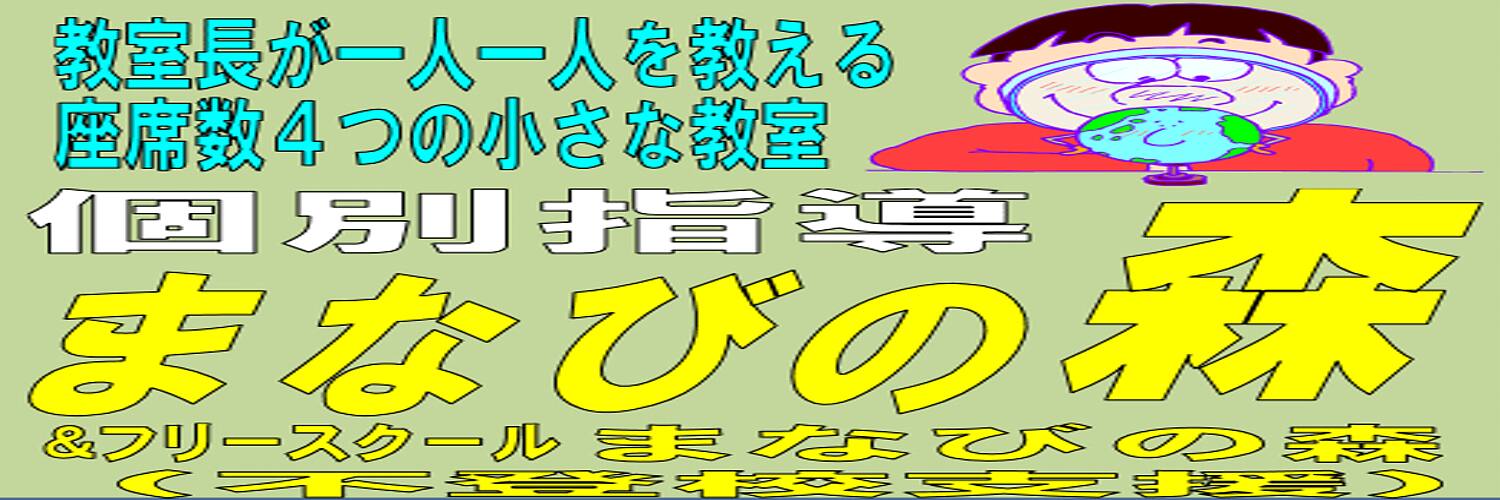
個別指導塾だからできる多様性を考慮した進路指導
一人一人の適正や興味を客観的に考慮して、それ以外の可能性についても提案しています。
幸せに生きていく上で、大切なのは本当に納得できる仕事に就くことです。
その時、大学進学が邪魔になることもあるのです
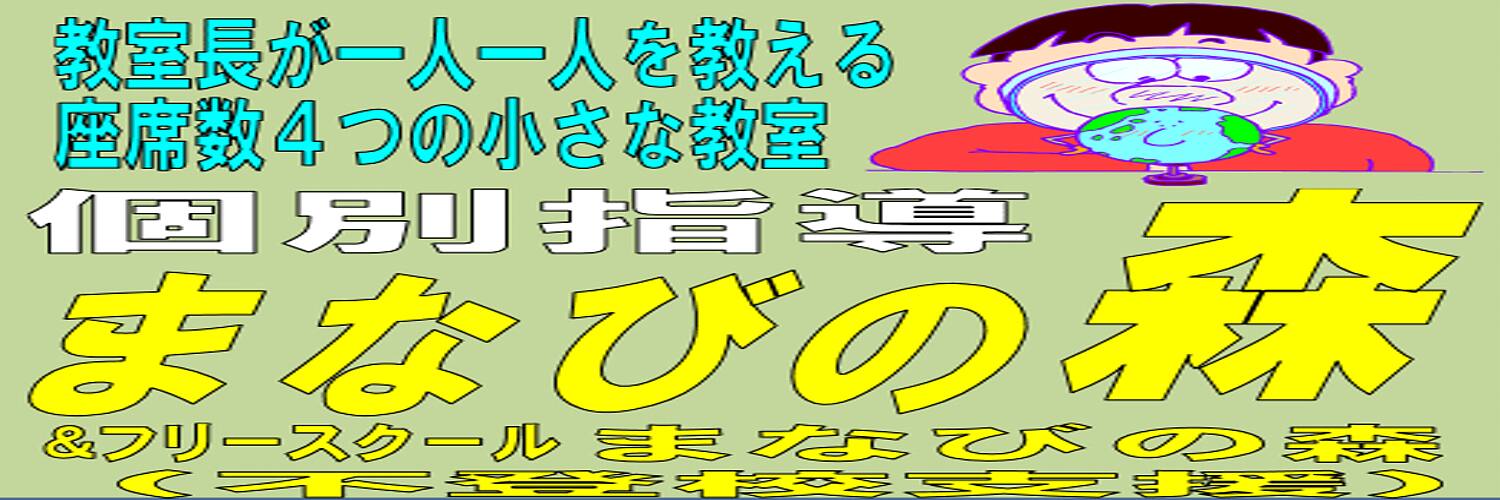
学習塾の役割の一つに進路指導があります。
しかし、多くの学習塾、特に大手と呼ばれる学習塾では、生徒本人の適性に応じた進路指導や相談を受けているとは思えない時があります。その一つが、全ての生徒があたかも大学に進学するのが当たり前という姿勢での指導です。
個別指導まなびの森では、お子さんの進路を考える時に、大学進学ありきでは考えません。
お子さんが何に興味があるのか?どんな仕事をしたいのか?を一緒に考えて、その為の筋道を考えます。
その筋道を決めてから、今の学力や、やる気を元に、高校はどこに行くのが良いか、大学に進むべきかどうか、大学に行くならどの学部で学ぶのが良いかを、よく考えて助言します。
ですから、お子さんの将来の希望によっては、普通科ではなく、工業科の高校をお勧めすることもあります。
保護者の方の中には、工業高校に行ったら大学に行けないから止めて欲しいという方もいますが、その考えは古いです。
今の工業高校では大学進学の割合も高く、望めばどこなりと進学できるところはあるのです。
ただ、工業高校で手に職を付けた人の多くは、その専門性で早く仕事をしたいと考えるのが普通なだけです。
それだけ、職業高校に進んだ子達は、自分のできることに自信を持っていて、自分の人生の在り方について明確になっていると言うことです。
残念ですが、普通科に進学した子どもには、大学に入っても自分が何を仕事にしたいのかが分からないまま、何となく就職する人が結構多いですね。
そして、そう言う子達は5年も持たずに会社を辞めてしまいます。
まなびの森では子どもたちにそのような未来を歩んで欲しくないと思っています。
確かに、保護者の方々の多くはお子さまが大学に進学することを望まれているかも知れません。
ただし、その理由が、「単純に大学卒業の方が将来有利だから」と言うのであれば、考え物だと思います。
大学卒業をして就職をすると、給与体系面で有利であることは事実です。
しかし、その仕事がお子さんの人生を幸せにしてくれるかどうか、充実したものにしてくれるかどうかは保証されていません。
私は、今の若いサラリーマンを見ていて、本当に充実して幸せかどうか怪しいと思っています。
また、そう言う面を抜きにしても、大学を卒業して就職をした仕事が本当に続けられるのか?と言う問題はすごく深刻になっています。
ですから、お子さま一人一人の興味、特性をしっかりと見つめて、将来の多様な可能性を示してあげないといけないと思うのです。
塾の進路指導が、目の前の受験する高校、大学を提示するだけになってはいけないのです。
あくまでも、もっと先を見据えた上での高校受験、大学受験でなければ、お子さまは将来道に迷うことになるかもしれないのです。
そのことを受け止めて、塾の進学実績などを考慮せずに、お子さんの最善となる進路を一緒に考えていきます。
以下、手前味噌でありますが、教室長の三人の子どもたちの進路について紹介します。
教室長が、どのような価値観を持って、子どもの将来を見ているのかを感じてもらえれば幸いです。
長男は、幼稚園の頃から虫が大好きでした。
そして、その頃から「虫博士」になるとずっと言っていました。
ですので、私は「なら、京都大学の理学部で勉強をすれば良いよ」と教えました。
本人は京都大学がどんなところかも知りませんが、「じゃあ、京都大学に行く」と言ってくれたので、そこから、京都大学に入り学んでいくための準備を始めました。
準備と言っても、勉強の詰め込みをしたり、お習いごとをさせたりするのではありません。
京都大学に入るのに必要なのは、手前味噌な学力ではないのです。
そうではなく、自分で考える力、自分で判断する力、多くの知識とそれを生かせる知恵だと思っています。
ですから、とにかく多くの経験をさせました。
秘密基地作り、大工仕事、プラモデル、好きな虫や生き物の絵を描いたり、粘土などで模型を作らせたり、釣りや昆虫採集、いろいろなところへの旅行、ボードゲーム、将棋など、、、
勉強については、小学校に入るまでは机の前ではさせることはありませんでした。
口頭で、様々な知識をたくさん対話の中で伝えるようにしました。
小学校からは、ベネッセのチャレンジを与えて一人でさせて、進捗の管理とたまにある質問に答えるだけでした。
これについては、中学を卒業するまで変わりません。
一人で考えて進められることが大事なので、人に依存しないように育てました。
当然ですが、私は長男に「勉強しろ」と言ったことはありません。
言ったのは、「自分の目標や目標があるなら、それに向けた努力を手を抜くな」と言うことです。
私としては、絶対に京都大学に進学して欲しいと思っていた訳ではありません。
あくまでも、長男の興味にあったことができるのが、そこだったと言うだけです。
ですから、勉強でスランプに陥った時などには、本気で「造形」の方へ進路変更しないかと伝えたくらいです。
でも、長男の夢は本気でした。
一年浪人はしましたが、無事に京都大学に入学することができました。
そして、大学では自分の好きなことをやり、楽しそうに毎日を過ごし、2025年に大学院を卒業して、希望だった研究職で就職することになりました。
次男は勉強嫌いでした。
小さい頃から、言葉がつたなくて、マイペース。
知能は長男と比べると少し低かったのですが、特に興味のあるものも無く、ただ楽しそうなことを見つけてはふらふらとしている感じの子どもでした。
でも、全体を見通す力は鋭く、ときどき大人をはっとさせるようなことを言う子どもでした。
小学5年生頃に将棋に興味を持ち、将棋教室に通うようになりました。
でも、まじめに定石を学ぶ訳でもなく、自己流で力を付けていきました。
高校の時にアマチュア2段にもなりました。
次男の勉強面については、長男に任せていました。
長男がいつも、次男との会話の中で、クイズのようにいろいろな事を質問しては、説明をしていました。
そのお陰で、あまり本も読まないのに、クラスでは物知りで通っていました。
勉強については、長男と同じベネッセのチャレンジを小学1年生より与えてさせていましたが、やはり、将来の目標がある訳でもなく、最低限のことだけして課題を提出するだけでした。
それでも、期限に遅れることなく課題を提出し続けるように私の方で進捗管理をして、中学三年生の時の五木の模擬テストでは偏差値は58ありました。
塾も行かず、目標がないまま一人でがんばった割には良くやったと思います。
中学3年の時に、進路の話をしていた時にも、「勉強はあまりしたくないから、大学には行きたくない」とはっきり言っていましたので、「じゃあ、工業高校に行こう」と進めました。
そして、次男は「現場の仕事がしたい」と言っていたので「建築科のあるところで考えよう」と言うことで、都島工業高校を受験しました。
工業高校の授業は昼からは実習で勉強はありません。
ですから、興味のもてる学科に入れると、一日の半分は遊びのような感覚になります。
次男はそんな環境で、毎日楽しそうに学校に行き、勉強をしないで良い分、毎週15時間のアルバイトもしながら、楽しく毎日を過ごしていました。
そんな毎日でも、学校ではいろいろな資格をとる機会を与えてくれて、いくつもの就職に便利な資格を取得していきました。
次男の友人の中には大学に進学する生徒もいました。
私は、次男に「大学にいくか?」と聞くこともありましたが、いつも「いや、働きたい」と答えていました。
そして、建築系の企業に現場監督として、無事就職しました。
私は就職の際に、「何年か働いて、やっぱり大学に行きたいと思ったら、会社辞めていつでも大学に入ったら良いんだよ」と伝えましたが、就職して4年経っても、未だに会社を辞める気配はありません。
会社では、大学卒の「後輩」相手に仕事の指導をして、毎日を楽しく働いています。
三男は甘やかされて育ったので、マイペースでのんびりしています。
将来についても、中学卒業するまでペットショップの店員になることが夢でした。
そんな彼は長男と次男に育てられたと言っても良いと思います。
三男も次男と同様、私はあまり手をかけなかったので、長男次男がいろいろな事を三男に教えていました。
お陰で三男もクラスでは物知りと言われていました。
勉強面ではやはりベネッセのチャレンジを小学1年から与えて、長男次男と同様に進捗管理だけ私がして、後は一人で進めさせていました。
三男の興味は妖怪やUMA(未確認生命体)と言うファンタジーなもので、まったく実用的なものではありませんでしたが、それはそれで末っ子と言うことで「かわいい」と言うことで済まされていました。
こんな調子でしたので、将来に大学で何かを学ぼうなどと言う気も無く、特に好きな科目がある訳でもないので、中学3年の時の進路の相談をしている時も、「高校を出たら、ペットショップに就職したい」と言うだけでした。
大学にはまったく興味を持たないので、とりあえず高校では勉強はほどほどで良いから、手に職を付けようと言うことになりました。
卒業したらペットショップに就職したら良いよということで、次男と同じように工業系の高校を勧めました。
高卒でペットショップで働くなら、普通科にこだわる必要はありません。
次男の楽しい高校生活を見ていた三男は、工業高校の受験を望みました。
ただ、三男は五木の模擬テストの偏差値が63ありましたので、とりあえずと言うことで、大阪公立大高専を受験することにしました。
万が一、合格すれば5年間遊べる。
そんな感じでの出願でした。
その結果は合格。
入学後、やはり週に15時間のアルバイトをしながらプログラムに関する勉強をして、気がつけばそちらに関心を持ったようで、5年生の時にはソフトウェアの会社への就職を希望するようになっていました。
高専での進路は求人数が100倍を超えることもあり、就職が圧倒的に多いのですが、大学3年への編入も希望すれば大抵はできます。
三男にも大学への編入をする気は無いかと確認しましたが、やはり就職したいと言う答えでした。
仕事に繋がる専門性を持つと、それに関する仕事をしてみたくなるもののようです。
三男にも、大学に行きたくなったら、いつでも会社を辞めても良いよと伝えていますが、今のところ、その様子はありません。
2025年より、ソフトウェア制作会社で働くことが決まって,楽しみにしています。。
その進路が正しかったかどうかは、誰が決めるのでしょう?
それははっきりしています。
子ども自身です。
親があれこれと口出しをして本人が納得していない進路を進ませるのは、大抵は失敗します。
大人の助言はとても大切です。
まだまだ知らないことだらけの子どもでは自分の進路を選ぶにも、その狭い知見でしか考えられません。
その狭い子どもの世界を広げて、いろいろな可能性を見せてあげるのが、大人の助言なのです。
でも、最後は本人が決めなければなりません。
自分で決めることで、子どもは自分の人生に責任感を持つことができるのです。
私はそう考えて、まなびの森の生徒と進路の相談をします。
迷っている生徒には、少しでも必要な情報を提供して、納得してどちらかを選べるように手伝います。
でも、決してそれを押しつけるようなことはしません。
そして、その選択がどんなものであっても,真剣に考えてのものであれば肯定します。
ですから、決して大学進学にはこだわりません。
偏差値だけで受験校を決めることもしません。
流行で何が良いと言うこともしません。
ただ、子どもの可能性を狭めることなく、その子が将来に笑顔でいられることが一番想像できそうな進路を考えます。
なぜなら、その選択が正しいかどうかは、収入の多さや、世間の評価では決まらないからです。
本人が幸せであるなら、それが一番正しいのです。
その正しい選択ができるようにお手伝いをします。

みんな、いろいろな進路で良いんだよ!